日本ではまだロゼワインの魅力は浸透していない!?
春になり、桜の季節がやってきました。桜の花びらを思わせる美しいピンク色をしたロゼワインは、この時期にぴったりのワインですが、日本ではまだまだ日常的に飲まれる機会は少ないようです。私が働いているお店でも、お客様からロゼワインを求められることはあまりありません。
世界的に見るとロゼワインの消費量は年々増え続けており、特に欧米諸国では「気軽に楽しめるオシャレなワイン」として、とても人気なんです。対して日本では長らく「ワインといえば赤か白」というイメージが根強く、ロゼワインはどこか中途半端な存在として、なかなか定着していません。
日本では「ロゼワイン=甘い」というイメージがあるのも、ロゼが敬遠される原因になっているようにも思えます。

「辛口のワインをお願いします」という言葉をよく聞く日本ではロゼワインに対して、昔出回っていた「甘口ワインではないのに甘味が強すぎるワイン」のイメージが残ってしまっていると常々感じています。かつては甘いワインとしてのイメージの強かったロゼワインですが、近年は「辛口で本格的な味わいのもの」が主流になっていることはご存じでしょうか?
白ワインや赤ワインには、「前菜や軽めの料理には白ワイン」、「お肉料理にはしっかりとした赤ワイン」といった、ワイン選びの明確なイメージがあるのに対して、ロゼワインはどんな時に飲めばよいかというイメージが曖昧なことも、選ばれづらい理由の一つでしょう。
しかし見方を変えれば、そんな曖昧なロゼワインこそ、実は「ご家庭にぴったりの万能ワイン」なんです。今回のコラムで、ぜひロゼワインの魅力を知ってもらいたいと思います。
実は万能なロゼワイン、合わせる料理も幅広い!
ではロゼワインの良いところを紹介していきましょう。先ほどロゼワインは中途半端な存在だという表現をしてしまいましたが、実はそこがロゼワインのとても良いところでもあるのです。赤でもなく白でもない、「赤と白の両方の良さを兼ね備えた万能ワイン」ということです。その魅力は、何と言っても飲むシーンを選ばない万能性。
たとえば、「今日の夕飯は何を作ろうかな?」と迷った時、ロゼワインであれば、だいたいの料理に寄り添ってくれます。赤でも白でもないので、料理をワインに合わせて考えて作る必要が無くなります。

飲みたいワインの好みがご夫婦で分れてしまった場合にもおすすめです。後に説明するセニエ法で造ったロゼワインには赤ワインのような風味がありますので、赤ワインが飲みたいと思った人にも寄り添っていますし、赤ワイン程の渋みはなく、白ワインに近いスッキリ感もありますから、白がお好きな方でも楽しめます。
「今日はワインに合う料理を準備したいけれど、料理の好みが家族みんなバラバラ……」そんな時にもロゼワインは大活躍すること間違いなしです。和洋中どんなジャンルでも自然に寄り添ってくれます。
特に和食との相性が非常に良いので、お刺身や寿司はもちろん、唐揚げや焼き鳥といった家庭料理にもピッタリなのがうれしいところです。
醤油や甘辛いタレなど日本特有の調味料を使った料理とも相性抜群で、鶏肉やブリの照り焼きなども好相性。また、トマトソース系のパスタ、ピザ、シーフード料理、さらにはチーズやクリーム系の料理でも合わせていけます。ロゼワインの持つ程よい酸味と果実味、そして白ワインにはない複雑さが、多彩な料理の美味しさを引き立ててくれる、困ったときこそ本当にありがたい存在です。
ロゼワインの製法、色々あるって知っていますか?
先ほど触れたロゼワインの製法について、ご紹介します。実はロゼワインの作り方は一つではないんです。大きく分けると次の3つの製法があります。
①セニエ法 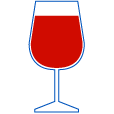
赤ワインを造る工程で、短時間だけ果皮と果汁を接触させて、ほどよい色味を抽出した後に果汁だけを抜き取って発酵させる方法です。途中までは赤ワインと同じ方法で作りますから、濃い色合いで、しっかりとした味わいのロゼワインになりやすいのが特徴です。なので、どちらかと言えば赤ワインが好み、という方にぜひおすすめしたいロゼワインです。
②直接圧搾法 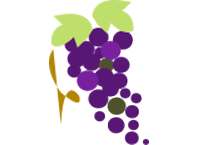
こちらは、黒ブドウを使って、白ワインのようにワインを醸造する方法です。黒ブドウの果汁を優しく絞り、程よく黒ブドウ由来の成分を抽出することで、きれいなピンク色の果汁となります。こちらの方法で造られたロゼワインは色味が淡く、より繊細で軽やかな味わいで、エレガントで爽やかなスタイルが特徴です。
③混醸法 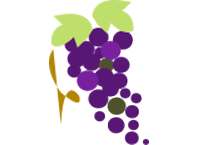

あまり一般的ではありませんが、黒ブドウと白ブドウを混ぜて発酵させる製法です。この製法は積極的に採用している産地が少ないので、あまり見かけない製法のロゼワインでもあります。かなり赤ワインに近いスタイルで、昔のボルドーでは一般的な手法でした。
簡単なご紹介となりましたが、特に「セニエ法」と「直接圧搾法」だけでも知っておくと、ロゼワイン選びのレベルがぐっと上がります。さらに産地や生産者によってその造りは様々ですから、より自分の好みや、その日の料理に合わせたワンランク上のロゼ選びに役立てていただければと思います。
ちなみに最初に買うロゼワインでお悩みでしたら、私のおすすめはやはり世界でも大人気、最も有名なフランス・プロヴァンス地方のロゼワインから試してみることをおすすめします。バカンスでも有名な南仏のプロヴァンスですが、実は生産されるワインの約9割がロゼワインというロゼの聖地でもあります。地中海の温かい気候で育ったブドウは、フレッシュな酸味と心地よい果実味があり、淡いピンク色で香り豊かなロゼワインとなります。王道から始めてみましょう。

休日にピッタリ! ロゼワインの楽しみ方
次に、どんなシーンでロゼワインが活躍するか、ロゼワインの飲み方、楽しみ方などについて、もう少しお話ししたいと思います。
まず、ロゼワインを飲むときの温度についてですが、少し冷やした10℃前後から飲み始めるのが良いと思います。よりスッキリと飲みたければ、もう少し冷やしても大丈夫ですし、先述のセニエ法のようにやや濃い目のロゼでしたら、温度を上げても美味しく飲めるでしょう。この幅広さもロゼワインの良さです。

さらに、賛否は分れるかもしれませんが、春が過ぎ夏の暑い季節には氷を入れて飲むのもアリです。氷を入れて少し薄めることでアルコール度数が下がり、ワイン初心者の方やアルコールに弱い方にも楽しみやすくなりますし、氷の入ったピンク色のグラスは涼しげで、夏の暑さを和らげ、気分を爽快にしてくれるはずです。
また、フルーツを入れて「ロゼワインのサングリア」にアレンジするのもおすすめです。イチゴやラズベリー、オレンジ、キウイ、そしてスイカなどを加えるだけで、見た目も華やかに、ホームパーティーや週末のご褒美タイムでも映える一杯に早変わりします。
プロヴァンスのおかげで、あまりロゼワインの浸透していない日本でも「ロゼ=バカンス」のイメージがある程度定着しています。それだけに、例えばお花見やピクニックなど、この桜の季節に春の陽気の中で楽しむロゼワインは、皆さんの休日を見た目にも気持ち的にも華やかに彩ってくれるでしょう。サンドイッチやピンチョスなど、手軽につまめる料理で十分楽しめるのもロゼワインならではです。
ホームパーティーでも華やかなロゼワインは大活躍! この時期にロゼのスパークリングワインなどで乾杯すれば、お花見気分も相まって気分も上がりますよね。日々の疲れを癒すリラックスタイムにも最適です。それ以外にも、ぜひ皆さんの休日に合わせたロゼワインの楽しみ方を見つけてみてください。

まとめ
いかがでしたでしょうか? 今回のコラムで今まで見えなかったロゼワインの魅力が少しでも伝われば幸いです。日本でも今後、世界のようにロゼワインの人気が出てくる可能性は十分あると思います。みなさんも、気軽にご家庭の食卓にロゼワインを取り入れてみて下さい。
さて、皆さんがこのコラムをご覧になっている頃は、すでに桜が満開になっているでしょうか? ぜひ綺麗な桜の花を楽しみつつ、お好みのロゼワインを片手に、素敵な時間をお過ごしください。
監修

牧野 重希(まきの しげき)
吉祥寺の老舗イタリアン、リストランテ イマイのシェフソムリエ。2007年、料理人を志しリストランテ イマイに入社。2010年よりセコンドシェフとして従事。料理を学ぶなかでワインの魅力に惹かれ、お客様へのより良いサービスとワインの提供を目指し、接客に転向。
2023年からWEBサイト「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ」の講師に着任。
RISTORANTE IMAI:http://www.ristoranteimai.com/
- ・2013年 ソムリエ取得
- ・2017年 ソムリエ・エクセレンス取得
HOUSING NEWSハウズイングニュースとは
私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。





